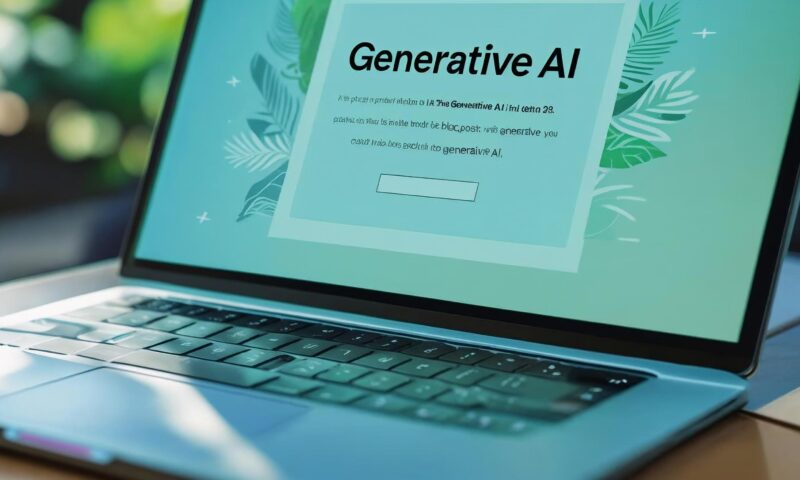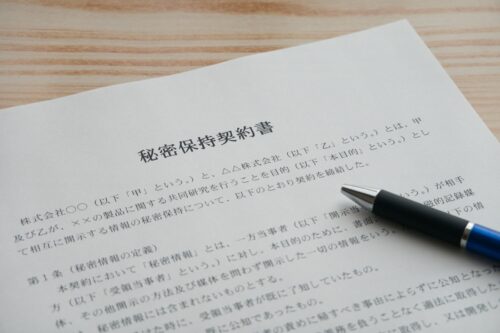1.はじめに
昨今、生成AIが急速に普及しており、ビジネスの場面で利用されることも増えてきているような印象を受けています。
生成AIとは、人間が入力した指示や質問(これを「プロンプト」といいます)に応じて、文章・画像・音声・動画などの新しいコンテンツを自動で作り出す人工知能のことをいいます。これまでのAIは、あらかじめ決められたルールやデータに基づいて答えを選んだりするものであったのに対して、生成AIは、学習した大量のデータからパターンを理解し、それをもとにゼロから新しい文章や画像を作成できるなどの点で、これまでのAIと大きく異なります。
このように生成AIは大変優れたツールであるものと思われますが、生成AIの利用に関して注意が必要な場面もあります。特に、生成AIをビジネスで利用する場合には、生成AIに情報を入力する場面や、生成AIによる生成物を利用する場面などで、法律や契約などとの関係で細心の注意を払う必要があるように思われます。
そこで、今回は代表的な生成AIであるChatGPTを例に、よくお聞きするご質問に回答させていただきます。
| ①ChatGPTに入力したプロンプトをChatGPTの学習のために使われ、他人に共有されてしまわないかが心配ですが、対処法はありますか? ②ChatGPTのプロンプトに入力しない方がよい情報などはありますか? ③ChatGPTで生成された情報などは、どのように利用しても問題ありませんか? ④自社の社員の一部が仕事でChatGPTを利用しているようですが、利用のルールなどを決めておかなくても大丈夫ですか? ⑤生成AIの利用法や注意点などについて、個別相談や社内研修をお願いすることは可能ですか? |
2.ご質問内容への回答
(1)ChatGPTの設定(ご質問①について)
| ①ChatGPTに入力したプロンプトをChatGPTの学習のために使われ、他人に共有されてしまわないかが心配ですが、対処法はありますか? |
ChatGPTに入力したプロンプトをChatGPTの学習のために使われたくない場合には、ChatGPTの設定を変更したり、ビジネス用のプランでChatGPTを利用することが考えられます。
ChatGPTの設定の変更については、具体的には、ChatGPTのプロフィールアイコンをクリック→設定を選択→データコントロールに移動→「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにすることが方法として考えられます。
特にビジネスの場面でChatGPTを利用する場合には、上記の設定をオフにされることをお勧めします。
ビジネス用のプランでChatGPTを利用する場合には、より強固なセキュリティ対策を講じられることが予想されます。
なお、上記のように対応した場合でも、入力したプロンプトの内容自体は、(少なくとも一定期間は)ChatGPTに保存されるものと思われます。
そのため、(2)でも回答するとおり、個人情報や営業秘密にあたる情報など、外部に知られてはいけない情報については、安易に入力しないことをお勧めします。
(2)プロンプトへの入力(ご質問②について)
| ②ChatGPTのプロンプトに入力しない方がよい情報などはありますか? |
例えば、個人情報や営業秘密にあたる情報など、外部に知られてはいけない情報については、ChatGPTのプロンプトに安易に入力しないことをお勧めします。
個人情報については、個人情報保護法でルールが定められています。例えば、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならず、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知または公表しなければならないこととされています。
この点、仮にChatGPTのプロンプトに個人情報を入力すると、例えば、上記の利用目的との関係で、利用目的の達成に必要な範囲内かどうかが問題となります(その他の注意点も含め、詳細は個人情報保護委員会のウェブサイトで公表されている令和5年6月2日付「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」をご参照ください。)
また、営業秘密については、一定の要件を満たすことにより不正競争防止法によって保護される場合があります。不正競争防止法では、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(一般的には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件などと言われています)こととされており、これらの要件に該当する場合に不正競争防止法の保護を受けられるものと考えられています。
この点、仮にChatGPTのプロンプトに不正競争防止法上の営業秘密を入力すると、上記①の秘密管理性が失われる可能性があり、入力した情報について不正競争防止法の保護を受けられなくなる可能性があることが指摘されています。
特に、他社との契約に基づいて他社から提供され、契約上の秘密保持義務が課されている秘密情報をChatGPTのプロンプトに入力すると、秘密保持義務違反になる可能性もあります。
これらについては、例外的な措置や解釈などもあり得るところですが、慎重にご検討いただいた方がよいように思われます。
(3)生成された生成物の利用(ご質問③について)
| ③ChatGPTで生成された情報などは、どのように利用しても問題ありませんか? |
生成AIによる生成物を利用する前に、その生成物の内容が正確であるかどうかを入念に確認する必要があります。実際、ChatGPTにも「ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。」と書かれており、ChatGPTが誤情報を生成する(「ハルシネーション」と呼ばれています)こともあり得ますので、注意が必要です。
また、生成物の利用が、著作権などの他人の権利を侵害しないかどうかを確認することも重要です。
生成AIによる生成物と著作権については、しばしば議論されるところではあります。
例えば、生成AIによる生成物が画像だとしますと、その生成された画像と、第三者が作成し著作権で保護されている画像が類似している場合、生成物が第三者の著作権を侵害する可能性があります。
プロンプトとして意図的に第三者の著作物を利用した場合はもちろんのこと、自分が認識していないところで生成AIが機械学習の一環として第三者の著作物を学習し、その結果、第三者の著作物と類似した画像が生成されることは起こり得ると思います。
そのため、特に生成AIによる生成物を対外的に利用する場合には、社内で入念に確認したうえで利用される方がよろしいものと思われます。
なお、生成AIによる生成物が著作権法上の著作物に該当するかなどの点については、文化庁ウェブサイト内「AIと著作権について」ページ(特に、著作権セミナー「AIと著作権」の各資料)をご参照ください。
(4)生成AIの利用に関する社内規程の作成(ご質問④について)
| ④自社の社員の一部が仕事でChatGPTを利用しているようですが、利用のルールなどを決めておかなくても大丈夫ですか? |
ChatGPTなどの生成AIの利用のルールを定めた社内規程を作成されることをお勧めします。
生成AIをビジネスで利用する場合、社員が自己の判断のみで利用することにより、個人情報、営業秘密などの情報漏えいや、著作権などの他人の権利の侵害などが起こることがリスクとして考えられます。
この点、例えば、生成AIを利用できる業務、生成AIに入力できない情報、生成された情報の利用、利用するAIツールの選定基準などに関するルールを社内規程として明らかにし、これを社内に周知しておくことで、上記のようなリスクを減らすことにつながるものと考えます。
生成AIに関する社内規程を作成する場合、事業規模や社員数などにより、作成手順や作成に必要となる期間が異なるものと思われます。
当事務所では、生成AIの利用に関する社内規程の作成などのサポートを承っております。
ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(5)生成AIの利用に関する個別相談や社内研修(ご質問⑤について)
| ⑤生成AIの利用法や注意点などについて、個別相談や社内研修をお願いすることは可能ですか? |
生成AIの利用法や注意点などについて、個別相談や社内研修での講義などをお受けすることは可能です。
これまでも、例えば、生成AIを利用して作成された契約書の内容などについて、リーガルチェックのご依頼、ご相談などをお受けしてきました。
また、生成AIの利用などに関して、商工会議所の経営相談員として個別相談をお受けしていますし、個別の企業様向けの講義なども承っております。
今後は商工会議所様でのセミナーや、司法書士の団体様での研修などで、生成AI利用時の注意点などについてお話させていただくことも予定されています。
生成AIの利用法や注意点の基本から、例えば、不正競争防止法上の営業秘密との関係性など、個別の法令や契約などについての講義にも対応しております。
オンラインでのご相談や講義も可能ですので、ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
3.当事務所のサポート例
当事務所では、各社様、各団体様のご要望を伺いながら、下記のご依頼、ご相談などを承っております。
| ・生成AIの利用を始めるにあたって、注意点やリスクなどを教えてほしい。 ・生成AIを利用して作成した契約書について、その内容を確認してほしい。 ・生成AIの利用に関する社内規程の作成や、その後の運用などを継続的にサポートしてほしい。 ・生成AIの利用法や注意点などについて、個別相談や講義を依頼したい。 ・生成AIと関連して、不正競争防止法などの個別の法令についての講義を依頼したい。 |
お気軽にお問い合わせください。